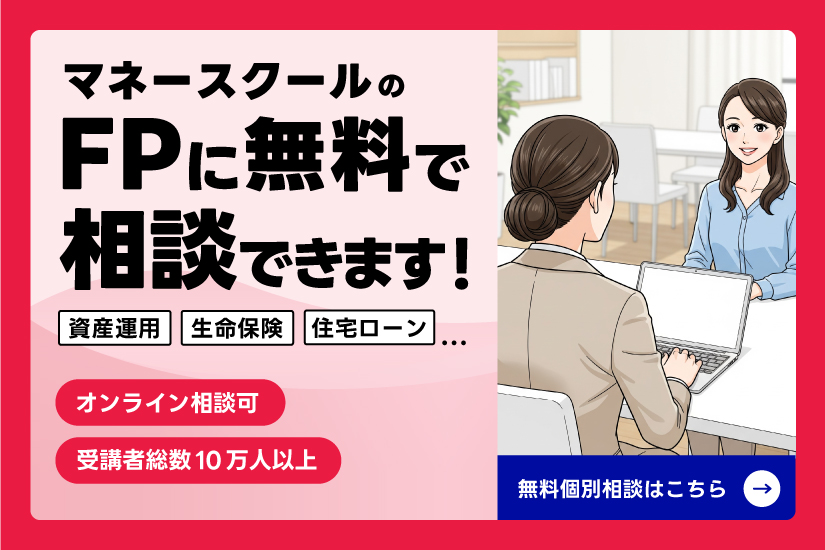「今年こそは貯金する!」と誓ったはずなのに、気づけばもう年の後半…。思うように貯金額が増えず、「やっぱり自分は意志が弱いんだ…」なんて落ち込んでいませんか?
貯金が続かないのは、決してあなたの意志が弱いからではありません。貯金へのモチベーションが続かないのにはちゃんとした「理由」があり、それを解決する「コツ」が存在するのです。
この記事では、多くの人が陥りがちな貯金が続かない理由、そしてその解決方法を具体的にお伝えしていきます。貯金への苦手意識を克服し、楽しい貯金への第一歩を踏み出しましょう。

1:なぜ?貯金のモチベーションが続かない3つの理由

実は、モチベーションが続かなくなるのには、いくつかの共通した理由があります。
主な理由として考えられるのは、次の3つです。
- 貯金の目的・目標が曖昧だから
- 我慢ばかりで楽しくないから
- 成果が実感しにくいから
ここでは、なぜあなたの貯金が続かないのか、その理由をひとつずつ見ていきましょう。
1−1: 貯金の目的・目標が曖昧だから
貯金が続かない大きな理由のひとつは、「何のために貯めるのか」というゴールがぼんやりしていることです。
「なんとなく将来のため」「とりあえず貯金」といった漠然とした理由では、人はなかなか頑張れません。それは、ゴールのないマラソンを走らされているようなもの。どこに向かっているのか分からなければ、走る気力がなくなるのは当然です。
日々の節約は、具体的な目的があって初めて意味を持ちます。「欲しいものを買う」「旅行に行く」といった楽しい未来像がないままでは、目の前の我慢はただの苦痛でしかなく、貯金そのものが目的になってしまいます。
これでは、モチベーションを保つのが難しいのも無理はありません。
1−2:我慢ばかりで楽しくないから
貯金が「楽しいこと」ではなく「辛いこと」などの”我慢”ばかりだと考えているからです。
貯金に対して、「節約」「我慢」「切り詰める」といったネガティブなイメージを持っていませんか?実際、お金を貯めるために好きなことを全て諦めてしまうと、生活はどんどん窮屈になります。
楽しみにしていた外食や趣味の時間を削ってばかりいると、日々の生活に潤いがなくなり、ストレスだけが溜まっていくのです。
このような「我慢だけの貯金」は、罰ゲームと同じです。人は、苦しいことばかりを長期間続けることはできません。やがて、「もう、できない」と我慢の限界が来て、反動で大きな買い物をしてしまうことも。
貯金が「楽しいこと」ではなく「辛いこと」と結びついている限り、継続は非常に困難になります。
1−3:成果が実感しにくいから
貯金を始めたばかりの頃は、成果が目に見えにくいため、達成感を得ることが難しいです。
コツコツ節約を頑張っているのに、通帳を見ても残高がほんの少ししか増えていない…。そんな時、自分の努力が報われていないように感じて、がっかりしてしまうことはないでしょうか。
例えば、毎月1万円ずつ貯金しても、1年で貯まるのは12万円。100万円という目標から見れば、まだまだ先は長いと感じるでしょう。
努力しているにもかかわらず、その成果が数字としてハッキリと表れないと、「自分の頑張りは意味があるのだろうか」と不安になり、続ける気力が失せてしまうのです。
2:貯金は楽しい!私の貯金のモチベーションはお金が増えていくのを楽しむこと
みなさんの貯金のモチベーションは何ですか?
私の場合、貯金額そのものが増えていく過程を楽しむことが、何よりのモチベーションになっています。通帳の数字が増えていくのを見ると、頑張りが成果として一目で分かり、純粋に楽しいと感じるのです。
例えば、私は銀行員時代、会社の財形貯蓄を利用していました。
毎月2万円ずつ給与天引きで貯蓄にまわしていたので、久しぶりに残高を見たときに「こんなに貯まっていたなんて!」と嬉しくなり、お金が増える楽しさでモチベーションが上がったのを覚えています。
みなさんにもぜひ、私が体験したことと同じように、「貯金が楽しい!」と思っていただけたら嬉しいです。
次の章では、FPの私が貯金を楽しむために実践していることをお伝えします。お金が増えていくことを楽しみながら、貯金を続けてみましょう。
3:今日からできる!貯金のモチベーションを上げる・維持する6つの方法

具体的にどうすれば貯金を楽しめるようになるのでしょうか? ここからは、私が実際に試し、効果があったと感じているモチベーションを上げる方法を6つ紹介します。
- 「何のため」を明確にする
- 小さな目標達成で自分を祝う
- お金が貯まるのを見て楽しむ
- お金が貯まるのを誰かと共有して楽しむ
- 資産運用でさらに増やして楽しむ
- 貯金のための手間や労力をかけず、自分の生活を楽しむ
難しいものはひとつもありません。自分にできそうなものから、ぜひ試してみてください。
3−1:「何のため」を明確にする
大切なのは、「何のために貯めるのか」というゴールを具体的に描くことです。
漠然と「100万円貯める」と考えるのではなく、「1年後に沖縄でダイビングをするために20万円貯める!」といった、情景が目に浮かぶようなワクワクする目標を立てましょう。
目的がハッキリすると、日々の行動に意味が生まれます。例えば、毎日のコンビニ通いを週3回に減らすことが、「沖縄の青い海に近づくための一歩」だと思えれば、自然と頑張れるはずです。
目標は紙に書き出して部屋に貼ったり、スマートフォンの待ち受け画像に設定したりして、いつでも思い出せるようにしておくと、さらに効果が高まります。
3−2:小さな目標達成で自分を祝う
「我慢ばかりで楽しくない」という状態を避けるために、自分へのご褒美が欠かせません。
「1ヶ月で1万円貯まったら、ちょっとリッチなカフェでケーキを食べる」「10万円達成したら、欲しかったスニーカーを買う」など、自分を祝うルールをあらかじめ決めておきましょう。
この「ご褒美」が、貯金の道のりにおける楽しいイベントになります。大切なのは、貯金額に対して無理のない範囲で、自分が心から「嬉しい」と思えるご褒美を設定すること。
これにより、「貯金を頑張れば、良いことがある」と脳が学習し、ポジティブな気持ちで貯金を続けられるようになります。
3−3:お金が貯まるのを見て楽しむ
成果が実感しにくいなら、お金が貯まっていく様子を「見える化」して楽しむのが一番です。
最近では、銀行の公式アプリや家計簿アプリを使えば、スマートフォンひとつでいつでも簡単に残高や資産の推移を確認できます。
アプリを開いて、資産を示すグラフが右肩上がりに伸びていくのを眺めるのは、想像以上に嬉しいものです。自分の頑張りが数字やグラフとしてハッキリと表れるのを見ると、ゲームのレベルが上がるような感覚で達成感を味わえます。
これが「もっと増やしたい!」という強力なモチベーションに繋がるのです。わざわざ銀行に行って記帳しなくても、手元で手軽に進捗が確認できる。この「見える化」こそ、現代における貯金の楽しみ方のひとつです。
3−4:お金が貯まるのを誰かと共有して楽しむ
お金が貯まるのを一人で確認するだけでなく、誰かと共有することで、より楽しむことができます。
一人で達成感に浸るだけでなく、誰かと喜びを分かち合うことで、貯金はもっと楽しくなります。私自身、社会人になりたての頃は両親と貯金額を共有し、増えるたびに一緒に喜んだものです。
一人で貯めるよりも、誰かと一緒に貯まるのを確認した方が楽しみを共有できますし、途中で挫折しにくくなる効果もありますね。
先ほど通帳の残高を見て楽しむとお伝えしましたが、配偶者や両親など信頼できる人と一緒に、通帳残高を見て、残高が増えていくのを共有すると良いでしょう。
また、私がFPということもあり、親しい友人からも貯金の相談をされることもあります。
「お金のことは身近な人に相談しづらい」という人は、FPに相談し、プロの目線からアドバイスをもらうのも良いと思います。
3−5:資産運用でさらに増やして楽しむ
私は貯金の一部を資産運用に回し、さらに“増やして”楽しんでいます。貯金は確実に貯まっていきますが、大幅に増えることはありません。
しかし、資産運用をするとさらにお金を増やすことができるので、楽しみもさらに増えていきます。
私は、毎月一定の金額で投資信託を購入する方法で運用しています。初心者でも始めやすい、月々1万円ほどの少額からできる資産運用です。
初めはなかなか増えないことにがっかりすることもありました。それでも継続し、運用成果が出てくると、お金が増えていると分かり、モチベーションが上がりました。
さらに言うと、資産運用は長く続けることで、その金額はより大きくなっていきます。
下のグラフは、毎月1万円を20年間、
・投資信託で平均利回り7%で運用できた場合
・預貯金で利回り0%の場合
を比較したものです。

20年後、ただ貯めた場合の240万円に対し、運用した場合は524万円と、倍以上の差が生まれる可能性があるのです。
資産運用はリスクがあり、初めは怖いと思います。しかし、少額でも始めてみることで、大きなリターンを得られるかもしれません。
そうすると、お金が増える楽しみもさらに大きくなります。
3−6:貯金のための手間や労力をかけず、自分の生活を楽しむ
私は、貯金すること自体に手間や労力をかけず、自分の生活を楽しむように心がけています。細かいことに気を使いすぎると手間や労力がかかり、ストレスが発生し、生活そのものが楽しめなくなります。
例えば、毎月いくら貯金するかを計算したり、給与口座から貯金の口座にお金を移すことなど、ちょっとしたことでも毎月になると負担を感じてしまいます。
だからこそ、日ごろはお金のことを考えず、お金を貯めること自体に手間や労力をかけないことが大切です。そうすれば、余ったお金は使っていいので、自分の趣味や友達との食事などを楽しむことができます。
具体的な方法は、次の章でお伝えします。
4:モチベーションにかかわらず貯金をする方法
自動的にお金を貯める仕組みがあれば、モチベーションにかかわらず貯金をすることができます。
モチベーションを維持する方法は人それぞれですが、そのときの感情に左右されずに貯められる「仕組み」を作ってしまうのが最も確実です。
4−1:給与天引きや財形貯蓄など『自動的にお金を貯める仕組みを使う』
モチベーションに左右されず、貯金を続けるには、自動的にお金を貯める仕組みを使いましょう。
お金が手元にあるとつい使ってしまうという人でも、自動的にお金が貯まる仕組みを使えば、意識せずとも貯蓄に回せます。また、お金のことを考えすぎずに済み、ストレスを抱えません。
具体的には、口座引き落としや給与天引きができる積立定期や(※)財形貯蓄、あるいはクレジットカードでの投資信託の積立購入などを利用すれば、自分の意思とは関係なく自動的にお金を貯めることができます。
※財形貯蓄は勤務先の企業でこの制度を導入していないと利用ができないため、まずは勤務先に確認する必要があります。
実際に銀行員時代、貯金を上手に続けている人は、毎月の積立定期を利用している場合が多かったです。モチベーションを保つことが難しければ、自動的にお金を貯める仕組みを考えましょう。
4−2:自動的にお金を貯めるための『ルールを決める』
自動的にお金を貯めるには、金額やタイミングなどのルールを決めておくことが大切です。特に、毎月の収入がバラバラで貯金が難しいという人こそ、ルールを決めるべきです。
そうすることにより、計画的にお金を貯めていくことができ、貯金の目標額やゴールも見えてきてモチベーションにもつながります。
4−2−1:給与の一定額だけ手を付けない
給与が出たらまず、貯蓄に回して残ったお金で生活をする癖をつけましょう。「余ったら貯金する」のではなく、「先に貯金して、残ったお金で生活する」という流れを習慣にすることで、お金の使いすぎを防げます。
4−2−2:ボーナスの一定額には手を付けない
ボーナスの一定額は手を付けず、貯蓄や投資へ回すのがおすすめです。まとまったお金が入るボーナスは、使う楽しみも大きいですが、貯蓄や投資にしっかりと資金を回す絶好のチャンスでもあります。
4−2−3:給与が昇給したら一部を貯蓄や投資に回す
昇給したら、その一部あるいは全部を貯蓄や投資に回しましょう。昇給する前は今までの給与でやりくりできていたのならば、増えた分は貯蓄や投資へ回すことができるはずです。
5:まとめ
お金が増えることは楽しいことです。
私が実践している、貯金を楽しむ方法は以下の6つです。
- 「何のため」を明確にする
- 小さな目標達成で自分を祝う
- お金が貯まるのを見て楽しむ
- お金が貯まるのを誰かと共有して楽しむ
- 資産運用でさらに増やして楽しむ
- 貯金のための手間や労力をかけず、自分の生活を楽しむ
ぜひ真似してみてください。
そして、自動的にお金が貯まる仕組みを利用すれば、誰でも簡単に貯金を続けられるようになります。
楽しみながらお金を増やしていきましょう。
6:マネースクール101の無料個別相談
「お金のことを相談してみたいけど、誰に相談してよいかわからない…」
「自分にあった貯蓄や資産運用の方法が知りたい」
そんな方は、まずは無料でFP(ファイナンシャルプランナー)に相談をしてみませんか?
ご相談は来店またはオンラインで全国どこからでも可能です。
こんなことが相談できます
- 家計の見直し、ライフプランの作成
- 住宅購入の予算、住宅ローンの選び方
- 老後資金、教育資金の貯め方
- NISA、iDeCoの始め方
- 保険の加入、見直し
など
お金に関することをわかりやすく説明しますので、初心者の方もお気軽にご相談ください。
無料相談をご希望の方はこちらから!