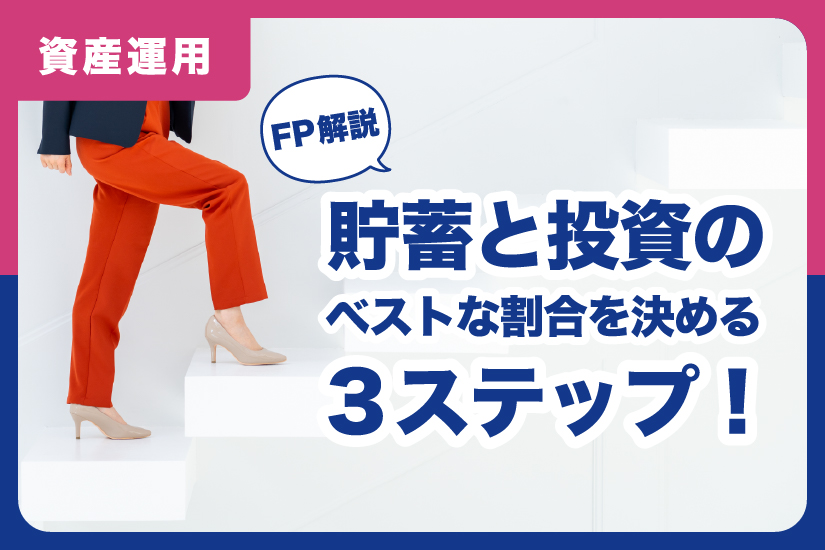「毎月しっかり働いているのに、なぜか月末にはお金が残らない…」。もし、あなたがこんな悩みを抱えているなら、その原因は「お金の管理方法」にあるのかもしれません。
じつは、FPへの相談でも非常に多いこの悩みの解決ポイントは、「口座の分け方」にあります。この記事では、お金が貯まらない原因から、具体的な解決策までをわかりやすく解説します。
この記事を読み終える頃には、「これなら自分にもできそう!」と、お金の管理に対する苦手意識が無くなっているはずです。

1:お金が貯まらない悩みは「給与口座」と「引き落とし口座」を分けることで解決!
お金が貯まらない悩みを解決するにはどうすれば良いか?多くの人が抱えるそんな悩みに対して、とてもシンプルで効果的な方法をご紹介します。
それは、「給与口座と引き落とし口座を分ける」ことです。たったこれだけのことで家計を改善できる可能性があります。
1−1:お金が貯まらない原因は、お金の流れが「見えない」こと
給料が振り込まれる口座から、家賃や光熱費、クレジットカードの利用代金、スマホの料金まで、すべてが引き落とされていませんか?この状態では、自分が「何に」「いくら使ったのか」を正確に把握するのが難しくなります。
いわゆる「どんぶり勘定」と呼ばれるこの状態は、けっして「だらしないから」「意志が弱いから」といった性格の問題ではありません。問題なのは、お金を管理するための「仕組み」が整っていないこと。お金の流れがごちゃ混ぜで見えにくくなっていれば、誰だって管理が難しくなるのは当然のことなのです。
1−2:解決策はシンプル!給与口座と引き落とし口座を分けるだけ
解決策はとてもシンプルです。給料が振り込まれる口座とは別に、支払い専用の「引き落とし口座」を一つ用意しましょう。
給料日になったら、まず「今月使う分」として決まった額を「引き落とし口座」に移します。あとはその範囲内でお金を使っていけば、自然と使いすぎを防げます。
たったこれだけで、お金の流れは劇的に「見える化」されます。複雑な計算や面倒な記録は一切不要。家計管理が苦手だと感じている人ほど、このシンプルな仕組みが効果を発揮するでしょう。
2:給与口座と引き落とし口座を分ける5つのメリット
ここでは、口座を分けることで得られる5つのメリットを解説します。
管理がシンプルになって支出が「見える化」されたり、挫折しがちな「先取り貯金」が自動化できたりと、その効果は多岐にわたります。
ひとつずつ見ていきましょう。
2−1:メリット1|家計管理がシンプルになり、支出を「見える化」できる
口座を分ける大きなメリットのひとつは、家計管理がシンプルになることです。給与口座は「お金を受け取る場所」、生活費用口座は「お金を使う場所」と役割を固定すれば、お金の流れが明確になります。
例えば、毎月初めに「今月の生活費」として10万円を生活費口座に移すと決めたとします。そうすれば、その口座の残高を見るだけで「今月あといくら使えるか」が一目瞭然になるのです。
わざわざ家計簿アプリにレシート情報を入力しなくても、通帳の記録やネットバンキングの明細がそのまま簡易的なお小遣い帳の代わりになります。
2−2:メリット2|「先取り貯金」で着実に貯まる
「余ったら貯金しよう」という考え方では、お金はなかなか貯まりません。これを解決するのが「先取り貯金」です。
給料が振り込まれた直後に、決まった金額(例えば月3万円)を「貯金専用口座」に自動で移す設定をしてしまうのです。一度設定すれば、あとは毎月あなたの代わりに銀行がお金を貯めてくれます。
意志の力に頼る必要はありません。貯金口座のお金は「最初からなかったもの」として生活することで、無理なく節約が習慣になります。
2−3:メリット3|目的別にお金を管理できる
お金を「目的別」に管理できるのも、口座分けの大きな魅力です。
「生活費」と「貯金」の2つに分けるだけでも効果はありますが、もう一つ「特別支出用口座」を作ると、さらに家計管理がレベルアップします。この口座の役割は、友人への結婚祝い、旅行資金、家電の買い替えなど、毎月ではないけれど、いずれ必ずやってくる大きな出費に備えることです。
毎月1万円ずつでも、この特別支出用口座に積み立てておけば、いざという時に慌てて貯金を切り崩す必要がなくなります。
2−4:メリット4|残高不足による引き落としミスを防げる
給与口座で生活費の支払いも、クレジットカードの引き落としも、すべてをまかなっていると、「うっかり使いすぎて、引き落とし日に残高が足りない!」という失敗が起こりがちです。引き落とし専用の口座を別に用意しておけば、こうしたリスクを軽減できます。
月の初めに、家賃や光熱費、通信費など毎月必ず出ていく固定費の合計額を生活費用口座へ入金しておきましょう。支払いの心配をすることなく、安心して残りの予算で生活できるようになるのは、精神的にも大きなメリットといえるでしょう。
2−5:メリット5|銀行の破綻やシステムトラブルのリスクを分散できる
複数の銀行に口座を持つことは、万が一の事態に備えるリスク管理の観点からも非常に重要です。
日本の金融機関は「ペイオフ」という制度によって、破綻しても預金者一人あたり元本1,000万円とその利息までは保護されます。複数の銀行に資産を分けておくことで、1,000万円を超える資産も守ることができるのです。
また、もっと身近なリスクとして、特定の銀行でシステム障害が発生し、ATMやネットバンキングが一時的に使えなくなる可能性も考えられます。そんな時でも、別の銀行に口座があれば、現金を引き出したり、振り込みをしたりと、いつも通りに行動できます。
3:口座を分けるための具体的な3ステップ

口座を分けるための具体的なステップは、次の3つです。
- 口座の「役割」と「数」を決める
- 目的に合った銀行で新しい口座を開設する
- 給料日後に「自動で」お金が移る仕組みを作る
この流れさえ押さえれば、もうお金の管理で悩むことはなくなるはずです。さっそく、具体的な手順を見ていきましょう
3−1:口座の「役割」と「数」を決める
何よりもまず大切なのは、「何のために口座を分けるのか」という目的を自分の中ではっきりさせることです。
- とにかく貯金を増やしたい
- 毎月の支出を把握したい
- 来年の海外旅行のために資金を貯めたい など
あなたの目標を具体的に思い描いてみましょう。目的が明確になることで、必要な口座の役割と数が見えてきます。
3−2:目的に合った銀行で新しい口座を開設する
口座の役割が決まったら、次はその役割に最適な銀行を選んで、新しい口座を開設します。
主な目的別口座の選び方のポイントは、以下の通りです。
貯金用口座
選び方のポイント①:金利が高い
選び方のポイント②:お得なキャンペーンがある
生活費用口座
選び方のポイント①:コンビニATMの手数料が無料になる
選び方のポイント②:アプリが使いやすい
最近では、本人確認書類をスマホのカメラで撮影して送るだけで、申し込みが完了する銀行も増えています。わざわざ平日に休みを取って銀行の窓口に行かなくても、自宅で簡単に口座を作ることが可能です。
3−3:給料日後に「自動で」お金が移る仕組みを作る
このステップが、口座分けを成功させるための最も重要なポイントです。それは、自分の意志や努力に頼るのではなく、「自動で」お金が動く仕組みを最初に作ってしまうこと。
例えば給料日が毎月25日なら、26日に給与口座から「生活費用口座」や「貯金用口座」へ、決まった金額を自動的に振り分けられるように設定します。
各銀行が提供している「定額自動入金サービス」や「定額自動振込サービス」を利用すると良いでしょう。特に、振込手数料が無料になることが多い「定額自動入金サービス」が使える銀行を選ぶのがおすすめです。
4:給与口座を分ける際の3つの注意点とその対策
口座を分ける際に、知っておきたい注意点は以下の3つです。
- 注意点1:口座の管理が面倒に感じる
- 注意点2:お金を移動させるときに手数料がかかる
- 注意点3:会社の指定で給与口座が変えられない
「口座が増えて管理が大変そう」「お金を移すたびに手数料がかかるのは嫌だな」「そもそも会社の指定で給与口座を変えられない…」といった、多くの人が抱えるであろう具体的な懸念について、その解決策をわかりやすく解説していきます。
4−1:口座の管理が面倒に感じる
複数の口座を持つと、キャッシュカードや暗証番号が増え、それぞれの残高を把握するのが少し面倒に感じられるかもしれません。せっかく家計をシンプルにするために始めたのに、管理が複雑になってしまっては本末転倒です。
この問題を解決するのに有効なのは、複数の銀行口座を一元管理できるスマホアプリの活用です。銀行が公式に提供しているサービスや、家計簿アプリを使えば、IDとパスワードを一度登録するだけで、すべての口座の残高や入出金履歴を一つの画面でまとめて確認できます。
4−2:お金を移動させるときに手数料がかかる
せっかく貯金をしようと意気込んでも、給与口座から別の口座へお金を移すたびに数百円の振込手数料がかかっていては、元も子もありません。このコストの問題を解決することが、口座分けを成功させるための重要なポイントです。
対策はシンプルで、手数料がかからない方法を選ぶこと。
おすすめなのが、多くのネット銀行が提供している「定額自動入金サービス」です。これは、自分の他の銀行口座から、毎月決まった額を手数料無料で自動的に入金してくれるサービスです。
また、銀行によっては、月に数回まで他行への振込手数料が無料になる特典が付いている場合もあるので、口座開設の際には手数料の条件を必ずチェックしましょう。
4−3:会社の指定で給与口座が変えられない
「うちの会社は給与振込口座が指定されているから、口座分けなんてできない…」と諦めている方も多いのではないでしょうか。
会社の指定口座は、あくまで給料を一度受け取るだけの「通過点の口座」として割り切りましょう。そして、メインで使う生活費用口座や貯金用口座側で「定額自動入金サービス」を設定します。
これにより、給料日後に、会社の指定口座から自動的にお金を引き寄せることが可能です。この方法なら会社に手続きを依頼する必要もなく、自分の設定だけで口座の使い分けを実現できます。
FPおすすめ!口座の分け方モデルケース3選
ここでは、目的別の口座分けモデルケースを以下の3つのレベルに分けてご紹介します。
・初級編:「給与受取」「生活費用」「貯金用」の3つに分ける
・中級編:「給与受取」「生活費用」「貯金用」「特別支出用」の4つに分ける
・上級編:「給与受取」「生活費用」「貯金用」「特別支出用」「投資用」の5つに分ける
初級、中級、上級と、それぞれのライフステージや目標に合わせて、あなたにぴったりのスタイルがきっと見つかるはずです。ぜひ、ご自身の状況と照らし合わせながら、最適な家計管理のかたちを探してみてください。
3−1:初級編|「給与受取」「生活費用」「貯金用」の3つに分ける
家計管理の初心者や、とにかくシンプルに始めたい方におすすめなのがこのモデルです。給与が振り込まれる口座はあくまで「お金が通過する場所」と割り切り、新たに以下の2つの口座を開設して家計を管理します。
生活費用口座
役割:毎月の生活費(家賃、光熱費、食費など)の支払いや引き落とし
ポイント①:1ヶ月分の予算だけを移す
ポイント②:残高=今月使えるお金
貯金用口座
役割:先取り貯金でお金を貯める
ポイント①:給料日にすぐお金を移す
ポイント②:目標達成まで使わない
たったこれだけで、「使えるお金」と「貯めるお金」が明確に分かれ、驚くほど管理が楽になることを実感できるはずです。
3−2:中級編|「給与受取」「生活費用」「貯金用」「特別支出用」の4つに分ける
基本の家計管理に慣れてきたら、「特別支出用口座」も準備しましょう。
急な出費で貯金を切り崩してしまう事態を防ぎ、より計画的なお金の管理が可能になります。
特別支出用口座
役割:年に数回の大きな出費に備える
ポイント①:結婚祝い、旅行、税金、家電購入など
ポイント②:毎月少しずつ積み立てる
この「特別支出用口座」があるだけで、「せっかく貯めたお金に手を出してしまった…」という罪悪感から解放されます。
3−3:上級編|「給与受取」「生活費用」「貯金用」「特別支出用」「投資用」の5つに分ける
貯金が習慣化し、さらに積極的にお金を増やしていきたい方向けの上級者モデルです。お金の役割を「使う」「備える」「貯める」「増やす」の4つに細分化し、盤石な家計の土台を築きます。
投資用口座
役割:お金に働いてもらい、将来のために増やす
ポイント①:NISAやiDeCoを活用
ポイント②:証券口座と連携し、毎月積立投資
「投資用口座」まで仕組み化できれば、日々の支出管理に悩むことなく、将来に向けた資産形成を自動的に進められます。
4:まとめ
本記事では、給与口座と引き落とし口座を分けることのメリットや、具体的な口座管理について解説しました。
「お金が貯まらない」という悩みの多くは、お金の流れが不明確なことが原因です。しかし、口座を分けてそれぞれの役割を明確にするだけで、驚くほどシンプルに、そして自動的にお金の管理ができるようになります。
ご紹介したモデルケースを参考に、まずは「生活費用」と「貯金用」の2つの口座に分けることから始めてみませんか。口座分けは、あくまで家計改善のスタート地点です。さらにその先の資産形成やライフプランニングに興味が湧いたら、ぜひ専門家であるFPにご相談ください。
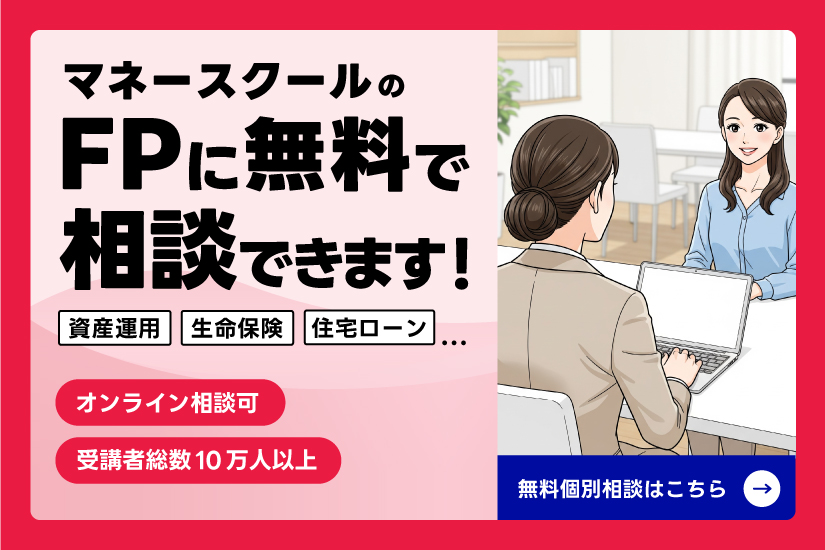






のための賢い5つの節約術.jpg)