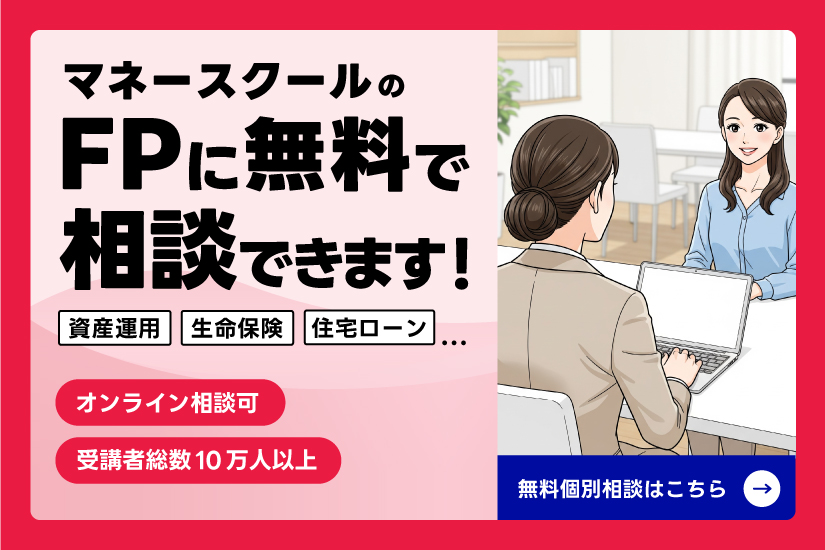「貯金が500万円貯まったら、今の仕事を辞めて転職しようと思っています。そして学校に通って貯金を取り崩して生活することを考えています。どのくらい暮らせるのか?長く暮らすためにできることを知りたいです。」
この方は、仮に月の生活費が20万円だとすると、500万円をそのまま取り崩して約2年暮らせます。
ただ、貯金だけで暮らす場合、仕事をしているときから支出が変わるといった注意点もあり、対策を考えておくとよいでしょう。
また、収入面では助成制度を活用することによって、暮らせる期間を延ばすことも可能です。
この記事では、貯金500万円で何年暮らせるのかというシミュレーションや、貯金だけで生活するための注意点と対策について説明していきます。
この記事でわかること
- 貯金500万円で、仕事をせずに何年暮らせるか(生活費別)
- 500万円の貯金だけで暮らすための注意点と対策
- 転職や起業を目指す人が得られる手当や助成制度
貯金が500万円あれば月20万円取り崩して約2年暮らせる
貯金が500万円あれば、毎月20万円を取り崩して約2年暮らせます。
(500万円÷20万円=25ヶ月)
以下に、毎月の生活費別で暮らせる期間をまとめました。

このように、 貯金500万円をそのまま生活費に使うために取り崩すだけだと、すぐに使いきってしまうことが分かります。
特に転職や起業など次のステップを考えている人は、貯金だけで少しでも長く暮らせると安心ですね。
そこで、次の章以降では、500万円の貯金で少しでも長く暮らすための方法についてみていきます。
500万円の貯金だけで暮らしていくための支出面での注意点と対策
500万円の貯金だけで暮らす場合、仕事をしていた人もいったん辞めることになります。
そうすると、仕事をしていた時とは支出面で変わることがあるので注意が必要です。
貯金だけで少しでも長く暮らすためにも、まず仕事を辞めた場合に支出がどう変わるかを知ることは大切です。
そのうえで、支出を抑える対策をとれないかを考えましょう。
以下より、ポイントとなる主な支出ごとに注意点と対策をみていきます。


健康保険は負担が少なく済む方法を選択する
会社員として働いているときは、通常は健康保険に加入しています。
その場合、健康保険料は毎月給与から天引きされていました。
それが仕事を辞めると、保険料負担がどう変わるかを3つの選択肢から順番にみていきます。
ポイント!
健康保険をどうするかで支出も変わるので、負担が少なく済む方法を選びましょう!
以下は、退職後2年間の保険料負担(30歳単身、在職時年収300万円、退職後仕事をしないケース)です。

※令和6年度、東京都世田谷区在住で計算
※2年目も保険料率を同じにして計算
3つの選択肢をそれぞれ見ていきましょう。
①家族の扶養に入る
まず初めに、健康保険に加入している家族(親や配偶者)がいる場合、その扶養に入ることを検討しましょう。
この場合は、保険料負担がなく、支出は増えないからです。
②国民健康保険に加入する
次に、国民健康保険に加入することが考えられます。
その場合は、国民健康保険料を支払うことになります。
国民健康保険料は、前年の所得を基準に市町村ごとに保険料が変わります。
なので、退職して1年目は保険料が比較的高くなります。
もっとも、仕事を辞めて働かない場合は、2年目以降は保険料は下がります。
③健康保険を任意継続する
さらに、退職した会社の健康保険に引き続き加入(任意継続)することが考えられます。
その場合の保険料は、会社と折半だったものがすべて自己負担となり、2倍となるため保険料負担は増えます。
また任意継続の保険料を決める基礎となる報酬月額は2年間変わらないため、退職したあと無職でも2年目の保険料は高いままとなります。
そのため、任意継続を1年でやめて、2年目から国民健康保険に切り替えると、保険料が安くなる場合があります。
ポイント!
扶養家族がいる場合は、健康保険の任意継続にすると、被扶養者(配偶者や子)の分は保険料がいらないため国民健康保険よりお得になることもあります。
国民年金保険料の免除制度を利用する
会社員として働いている場合、通常は厚生年金に加入しているため、厚生年金保険料が毎月給与から天引きされます。
しかし、仕事を辞めると国民年金となるため、月16,980円の国民年金保険料を支払うことになります(令和6年度)。
この支出をおさえたい場合は、国民年金の免除や納付猶予制度を利用することが考えられます。
ただ、この制度を利用できるかは前年の所得で審査されるため、通常は仕事を辞めてすぐに認められるわけではありません。
参考:日本年金機構|国民年金保険料の免除・納付猶予制度について
仕事を辞めると税負担は減るが、退職した翌年の住民税の支払いは発生する
仕事を辞めると所得がなくなるため、所得税の負担は原則としてなくなります。
ただし、住民税については前年の所得を基準とするため、退職した翌年にも住民税の支払いが発生するため注意が必要です。
住まいを見直すと、大きく支出を減らすことも可能
現在の住居に住み続ける場合、家賃は変わりません。
ただし、会社から家賃補助が出ていた場合は、退職すると補助がなくなるため自己負担額が増えます。
家賃の負担を減らしたければ、家賃が安い物件に引越しをすることも選択肢として考えるとよいでしょう。
また、一人暮らしの人は実家がある場合、実家にいったん戻ると、家賃の負担そのものがなくなるため、支出を大きく減らすことも可能です。
固定費を見直して、毎月の支出を効果的に減らす
毎月の支出を効果的に抑えたい人は固定費を見直すとよいでしょう。
なぜなら、毎月一定額を支払っている固定費を見直すことで、その節約効果は今後もずっと継続するからです。
例えば、スマホの料金プランを見直したり、加入している保険料を見直すのもよいでしょう。
500万円の貯金だけで暮らしていくための収入面の対策
仕事を辞めて、500万円の貯金だけで暮らす場合は、仕事による収入が入ってきません。
なので、それを少しでも補い、長く暮らすために手当や支援制度を活用するという対策も考えておきましょう。
特に、ステップアップのために転職を考えていたり、起業したい人は知っておくと助けになりますので、うまく活用したいですね。
以下で、制度の概要や利用するための条件などをみていきます。
失業手当をもらう
仕事を辞めると、一定の条件のもと失業手当を受けることができます。
失業手当は自己都合の退職でも受けることができるので、ステップアップの転職を考えている人はぜひ活用しましょう。
失業手当をもらう条件
- 失業状態である(仕事がみつかれば就業する意思や能力がある)
- 退職前の2年間で雇用保険に通算12か月以上加入している
- ハローワークで求職申込をおこなう
参考:厚生労働省|雇用保険事務手続きの手引き 第13条「失業等給付について」
失業手当はいくらもらえる?
失業手当として受け取れる総額は、「1日当たりの支給額(基本手当日額)」と「給付日数」によって決まります。
・1日あたりの失業手当の金額の計算手順
退職直前の6か月に受け取っていた給与総額÷180
1で計算した金額に50%~80%を掛ける
・給付日数
退職理由と雇用保険の加入期間によって決まる
※会社都合の退職では最大330日もらえますが、自己都合の退職で90日~150日となります。
求職者支援制度を活用する
求職者支援制度は再就職や転職、スキルアップを目指す人を支援するための国の制度です。
この制度を使うと、主に2つの支援を受けることができます。
- 月10万円の生活支援の給付を受けることができる
- 無料の職業訓練を受講できる
ただし、この制度は原則として失業手当を受けることができない離職者が対象です。
なので、失業手当の受給が終わった人やそもそも失業手当がもらえない人におすすめです。
起業や開業したい人が活用したい助成制度
起業や開業を考えている人には国や地方公共団体による助成金や補助金もあります。
国の助成金や補助金など一例
- ものづくり補助金
- IT導入補助金
- キャリアアップ助成金
地方公共団体の助成金や補助金の一例
- 企業支援金
- 創業助成金
まとめ
500万円の貯金を取り崩して生活しようという場合、仮に月20万円の支出であれば約2年で使い切ってしまいます。
それでも支出面で対策をとることにより貯金で生活できる期間を延ばすことも可能なので、本文を参考にしてみてください。
また収入面での手当てや支援制度もありますので、利用できるものは利用しましょう。
さらに自分にできることを詳しく知りたい人はファイナンシャルプランナーに相談することをおすすめします。
マネースクール101の無料個別相談
「お金のことを相談してみたいけど、誰に相談してよいかわからない…」
「自分にあった貯蓄や節約の方法が知りたい」
そんな方は、まずは無料でFP(ファイナンシャルプランナー)に相談をしてみませんか?
ご相談は来店またはオンラインで全国どこからでも可能です。
こんなことが相談できます
- 家計の見直し、ライフプランの作成
- 住宅購入の予算、住宅ローンの選び方
- 老後資金、教育資金の貯め方
- NISA、iDeCoの始め方
- 保険の加入、見直し
など
お金に関することをわかりやすく説明しますので、初心者の方もお気軽にご相談ください。
無料相談をご希望の方はこちらから!