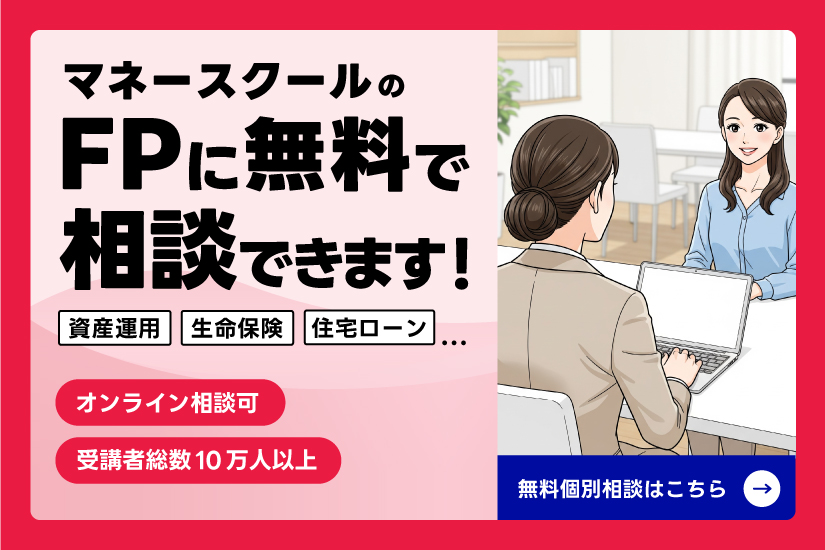「将来のために資産運用を始めたいけど、なんだかいろいろめんどくさそう…」
そんな風に感じて、一歩を踏み出せないでいませんか?
勉強や手続き、商品選びなど、資産運用にはたしかに面倒に感じるポイントがいくつかあります。しかし、その「めんどくさい」は、ちょっとしたコツで乗り越えることが可能です。
この記事では、あなたが感じている「めんどくさい」を解消し、賢く「ほったらかし」で資産運用を始める具体的な方法を解説します。難しい知識は一切不要です。この記事を読めば、きっと最初の一歩を踏み出したくなるはずです。

1:「資産運用がめんどくさい」と感じる4つの理由
ここでは、「資産運用がめんどくさい」と感じてしまう理由を4つ紹介します。
- 資産運用の勉強をしなくてはいけない
- 資産運用を始めるまでの手続きが大変そう
- どんな金融商品で始めたらいいか分からない
- 株価等の値動きを常に見ていなければならない
多くの人が、資産運用に対してこれらのハードルを感じています。共感できるポイントがないかぜひ確認してみてください。
1−1:資産運用の勉強をしなくてはいけない
資産運用を始めようと思ったとき、多くの人が最初にぶつかる壁が「勉強」です。
「経済のニュースを理解しなければ…」「専門用語を覚えなければ…」と考えると、それだけで気が重くなってしまいます。
実際に、資産運用には株式や投資信託、債券といったさまざまな種類があり、それぞれに異なる特徴やリスクが存在します。
金融庁の調査によると、日本では金融教育を受ける機会が少なかったこともあり、ほとんどの人が知識のない状態からのスタートです。だから、「難しい勉強が必須」と思い込み、「めんどくさい」と感じてしまうのです。
1−2:資産運用を始めるまでの手続きが大変そう
「資産運用を始めるには、まず証券口座の開設が必要です」と言われても、なんだか面倒な手続きを想像してしまいますよね。銀行口座を作った時のように、書類をたくさん書いたり、待たされたりするのでは…と考えてしまうかもしれません。
確かに、口座開設にはマイナンバーカードなどの本人確認書類が必要です。オンラインで申し込むにしても、たくさんの情報を入力する手間があります。また、「どの証券会社を選べばいいの?」という最初の選択肢でつまずいてしまう人も少なくありません。
申し込み後の審査を待つ時間も含め、取引をスタートするまでの道のりを考えると、「やっぱり大変そうだな」と二の足を踏んでしまう気持ちもよく分かります。
1−3:どんな金融商品で始めたらいいか分からない
なんとか口座を開設できたとしても、次に「何を買えばいいの?」という難問が待ち構えています。世の中には、数えきれないほどの金融商品が存在し、選択肢が多すぎることが、かえって私たちを悩ませる原因になります。
例えば、投資信託だけでも日本には6,000本以上あり、この中から自分にピッタリの1本を見つけ出すのは至難の業です。大切なお金を投じるからこそ、「絶対に失敗したくない」という気持ちが強くなり、なかなか決断できません。
結局、どれを選べばいいか分からないまま時間が過ぎてしまい、「商品選びがめんどくさい…」と感じてしまう人は非常に多いのです。
1−4:株価等の値動きを常に見ていなければならない
「投資を始めたら、毎日パソコンの画面に張り付いていないといけないのでは?」というイメージも、資産運用を面倒に感じさせる大きな原因です。
仕事中も株価が気になったり、価格が下がったらどうしようと不安になったり…そんな生活を想像すると、疲れてしまいそうですよね。
日々の値動きに一喜一憂して、精神的に消耗してしまうのではないか。本業やプライベートの時間がなくなってしまうのではないか。こうした時間的、精神的な拘束を考えると、「自分には向いていないかも」と感じてしまうのも無理はありません。
「常に監視しなくてはいけない」という思い込みが、資産運用へのハードルをぐっと高くしてしまっているのです。
2:資産運用の「めんどくさい」は仕組み化で乗り越えよう
資産運用は、じつは仕組み化することでめんどくささを回避できるケースもあります。
- 資産運用の勉強はセミナー参加で最短時間で学ぶ
- 資産運用の開始はFP(に手伝ってもらう
- 商品選びもFPに相談
- 運用中はほったらかしでOK
2−1:資産運用の勉強はセミナー参加で短時間で学ぶ
資産運用の勉強は、セミナー参加で短時間で学ぶことができます。
なぜなら、セミナーでは資産運用の大事な点をまとめて学ぶことができるからです。
例えば、資産運用初心者の方は、以下のような内容のセミナーに参加してみると良いでしょう。
- 資産運用の基礎知識(長期、分散、金利)
- NISAやiDeCoの制度について
- どの資金を資産運用に充てるべきか
自分で一からこれらの内容を学ぶとなると、相応の時間と手間がかかるでしょう。
資産運用の勉強は、セミナー参加が効率的です。
セミナーは無料のもので十分です。最近はオンライン形式も多いので、気軽に参加できます。

2−2:資産運用を始める際の手続きはFPに相談する
資産運用を始める際の手続きはFPにお任せできます。
例えば、以下のような面倒な手続きはFPがサポートしてくれるので、手間なくスムーズに資産運用を開始できます。
FPにおまかせできること(一例)
- 金融機関選び(おすすめの金融機関など)
- 口座開設に必要な書類の手配
- 口座開設の手続きサポート(証券口座、NISA口座)
資産運用開始までの、面倒な手続きはFPに相談して、手間なく最短でスタートしましょう。
2−3:商品選びもFPに相談で解決
難しい商品選びも、FPに相談することで解決できます。
例えば、投資信託についての基礎知識や、自分に合った商品の選び方のアドバイスを受けることができます。
商品について勉強したり、自分に合った商品を自分ひとりで一から探すのは、大変な労力になります。
商品選びをFPに相談することで、スムーズに資産運用を開始できます。
2−4:投資信託ならほったらかしでOK
金融商品はさまざまありますが、投資信託であれば、ほぼほったらかしで問題ありません。
個別株式投資のように、自分でタイミングを見計らって売り買いする必要はなく、投資信託は運用の専門家が投資家に代わって株式や債券の売買を行ってくれます。
そして、長期的に利益が出ることを目標として運用し続けてくれます。

そのため、私たちは買ったり売ったりする必要がなく、ほったらかし(長期で保持)でよいのです。
念のため、年に一回くらいは資産状況の確認をするのが望ましいです。このタイミングで担当のFPに相談すると良いでしょう。
3:資産運用はめんどくさい以上に価値がある
資産運用はめんどくさい以上に始める価値があります。
価値とはつまり、「資産が増える可能性」ということです。
資産運用は複利の効果によって、時間をかけてどんどん雪だるま式に増えていきます。
例えば、預貯金は金利が現在0.2%です。以前よりは金利が改善されたものの、大きな利回りは期待できません。
資産運用は、投資信託であれば年率6〜8%程度のリターンを期待できるものもあります。
以下は、毎月3万円を30年間積み立てた場合のシミュレーションです。預貯金(年利0%と仮定)と資産運用(年利2〜8%と仮定)を比べると、その差は一目瞭然です。

投資信託で『利率6〜8%』は現実的な数字
『リターン年率6〜8%』という数字は、例えば『MSCIコクサイ・インデックス』の過去の実績が参考になります。(2025年7月末時点のデータでは過去20年間の平均リターンは年率9.3%)
参照:my INDEX|MSCI コクサイ・インデックス (KOKUSAI)
※上記はあくまでも過去のデータです。将来のリターンを約束するものではありません。
長期的な資産形成を目指すなら、複利の効果を最大限に活かすためにも、一日でも早く始めることが有利に働きます。
頻繁に売買を繰り返すよりも、一度決めた方針でどっしりと長期間保有し続けることの方が、結果的に利益につながりやすいのが投資信託の特長です。
4:まとめ
資産運用そのものが分からなかったり、手続きが大変そうなど、始めるまでは確かにめんどくさいと思う要素は多いかもしれません。
ご自身で一から十までやるのは難しいですし、初心者であれば限界もあります。
そんなときは資産運用のプロ、FPに相談しながら進めることをおすすめします。
資産運用を始めて、将来『あのとき、めんどくさがっていたけど始めてよかった!』と思ってもらえたら幸いです。
5:マネースクール101の無料個別相談
「資産運用を始めてみたいけどどうしたらいいか分からない」
「NISAやiDeCoについて詳しく知りたい」
そんな方は、まずは無料でFP(ファイナンシャルプランナー)に相談をしてみませんか?
ご相談は来店またはオンラインで全国どこからでも承ります。
こんなお悩みが相談できます
- 自分に合った資産運用の選び方
- 効率よくお金を貯める方法
- 教育資金や老後資金の貯め方
- NISAの始め方
など
資産運用に関することをわかりやすく説明しますので、初心者の方もお気軽にご相談ください。
無料相談をご希望の方はこちらから!