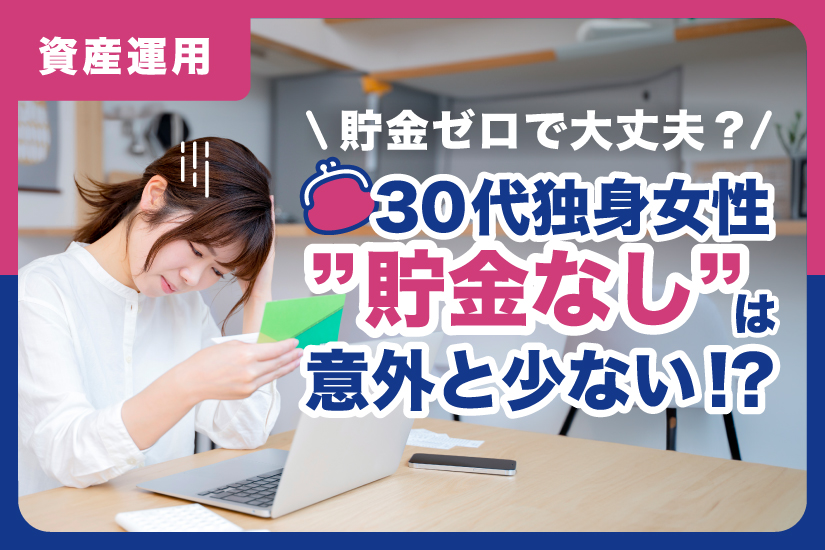家族の介護が必要になった時、あなたならどうしますか?
「仕事を辞めて介護に専念するしかない」と考える方も多いかもしれません。しかし、ちょっと待ってください。介護離職は、あなた自身や家族の生活、そしてキャリアに大きな影響を与えます。
この記事では、介護離職をしないために知っておきたい4つのポイントを解説します。
介護離職の不安を解消し、あなたらしい「仕事と介護の両立」のかたちを見つけてください。
介護離職とは?現状と問題点を理解しよう
介護離職は、本人や家族の経済状況に大きな影響を与えるだけでなく、社会にとっても大きな損失です。
ここでは、介護離職の定義や増加の背景、そして介護離職がもたらす様々なデメリットについて解説していきます。
介護離職の問題点を正しく理解して、仕事と介護の両立を実現していきましょう。
介護離職とは
介護離職とは、一言でいうと「家族の介護のために仕事を辞めること」。介護が必要な家族を支えるために、やむを得ず選択される場合が多いです。
具体的には、介護サービスの利用が難しい、家族の介護に十分な時間を確保できない、などのケースがあげられます。
介護離職者の増加とその背景
介護離職者の数は、近年増加傾向にあります。
この増加の背景には、高齢化や介護サービスの不足など、様々な要因が複雑に絡み合っているのです。
例えば、日本では高齢化が急速に進行しており、介護を必要とする高齢者が増加しています。厚生労働省の統計データによれば、要介護(要支援)認定者数は2023年3月に694万人とされています。

さらに、介護サービスの利用料の負担や、都市部ではそもそも介護サービスが足りないことも多いです。介護サービスが不足していると仕事をしながらの介護は困難になり、結果として離職につながるケースが増えています。
介護離職がもたらすデメリット(経済的損失、キャリアの中断、精神的負担)
介護離職は、介護者本人に多くのデメリットをもたらします。
まず、経済的な損失が大きいです。離職によって収入が途絶えることは、本人だけでなく家族全体の生活に影響を及ぼします。また、長年築き上げてきたキャリアが中断されることも大きなデメリットです。
さらに、介護による精神的な負担も見逃せません。介護と仕事の両立ができず、精神的に追い詰められてしまう人も少なくないのです。
これらのデメリットを総合的に考えると、介護離職は可能な限り避けるべき選択肢と言えるでしょう。
仕事と介護を両立するための4つのポイント
適切な準備と対応をすれば、仕事と介護を両立することは十分に可能です。ここでは、仕事と介護を両立するためのポイントを4つ紹介します。
- 介護保険制度や各種支援制度を理解する
- 介護の状況を職場に伝え、両立支援制度を活用する
- 介護サービスを利用し、負担を軽減する
- 一人で抱え込まず、相談窓口や周囲の協力を得る
自分に合った方法を見つけて、仕事と介護の両立に役立ててください。
ポイント1:介護保険制度や各種支援制度を理解する
介護保険制度や各種支援制度を理解することが大切です。
介護保険制度は40歳以上の人が加入します。これは、介護が必要になった時に費用の一部を負担してもらえる制度です。
また介護サービスには、自宅で受けられるもの、施設に通うもの、施設に入所するものなど様々な種類があります。
これらの情報を早めに収集することで、自分や家族に合ったサービスを選び、計画的に介護を進められるのです。
ポイント2:介護の状況を職場に伝え、両立支援制度を活用する
企業によっては、介護休業や短時間勤務などの支援制度があります。就業規則を確認したり、人事担当者に相談したりして利用できる制度を確認しましょう。
また、上司や同僚に介護の状況を伝えておくと周囲の理解や協力を得やすくなります。
例えば、急な休みが必要になった場合でも、職場からのサポートを受けられる可能性があるのでおすすめです。
ポイント3:介護サービスを利用し、負担を軽減する
介護サービスを賢く利用して負担を軽減することも大切です。
例えば、訪問介護では介護士が利用者の自宅を訪れ、食事や入浴、排泄などの介助を行います。また、ショートステイでは利用者が短期間施設に宿泊し、介護を受けることも可能です。
介護サービスを賢く利用することで、仕事と介護の両立がしやすくなるだけでなく、介護者自身の生活も安定するのです。
ポイント4:一人で抱え込まず、相談窓口や周囲の協力を得る
一人で抱え込まず、相談窓口や周囲の協力を得るようにしましょう。
例えば、地域包括支援センターは、介護に関する総合相談窓口です。ここでは、介護保険制度や介護サービスに関する相談だけでなく、介護者の悩みや不安などにも対応してもらえます。
家族や親戚、友人など、身近な人に協力を求めることも大切です。介護の悩みを相談したり、時には介護を代わってもらったりすることで、負担を軽減できるでしょう。
仕事と介護を両立した3つの事例を紹介
「実際に両立するのは難しいのでは…」と感じている方もいるかもしれません。
そこで、実際に仕事と介護を両立している方の事例を3つ紹介します。
- 複数の介護サービスを利用して介護負担を軽減
- 高額介護サービスを利用して介護負担を軽減
- 介護施設を利用して仕事と両立
これらの事例は、具体的なヒントや勇気を与えてくれるはずです。
事例1:複数の介護サービスを利用して介護負担を軽減
母親が要介護状態になったことをきっかけに、介護が始まったAさん。Aさんは、仕事の時間や休息時間を確保するために、複数の在宅介護サービスを利用しました。

これらのサービスを組み合わせ、毎月の介護費用を支給限度額内の約2万円に抑えました。
訪問介護で夕食の準備を手伝ってもらうことで時短勤務の回数が減り、日中は誰かの見守りがあるため仕事にも集中できたのです。
事例2:高額介護サービスを利用して介護負担を軽減
80代の父親(要支援1)と母親(要介護4)を持つBさん。母親の介護をする父親の負担を軽減するために、在宅介護サービスを毎日利用することにしました。
通院やリハビリが困難なため、訪問介護、訪問リハビリ、訪問看護を利用。また、夜間の心配もあるため、週に1回は夜間対応型訪問介護を利用しています。

介護費用が高額になったため、高額介護サービス費制度を活用。毎月の自己負担額を約27,000円抑えることができました。
Bさんは、1日1回両親やケアマネジャーに連絡して様子を確認し、月に1回は帰省して見守りを行っています。
事例3:介護施設を利用して仕事と両立
母親に介護施設に入居してもらい、仕事との両立を実現したCさん。
Cさんの母親は寝たきりの状態であり、つきっきりの介護が必要でした。仕事との両立が難しい状況の中で、「母親を介護付き施設へ入居する」ことを選択します。
施設では、食事や入浴などの日常生活の介護や健康管理を受けられます。

また、母親と世帯を分けることで、母親が非課税世帯となり、居住費や食費の負担を軽減できました。
これらの事例からは、介護施設や制度を効果的に利用することで、介護者の負担を大幅に軽減し、仕事との両立が可能になることがわかります。
▼介護費用を安くできた事例がたくさん載っています。
まとめ
介護離職は、本人や家族に大きな経済的・精神的負担をもたらすだけでなく、社会にとっても大きな損失です。
今回紹介した3つの事例のように、介護の形はひとつではありません。介護保険制度や介護サービスを賢く活用することで、仕事と介護の両立は十分に可能です。
大切なのは、自分だけで抱え込まず、できることから少しずつ行動を起こしていくことです。