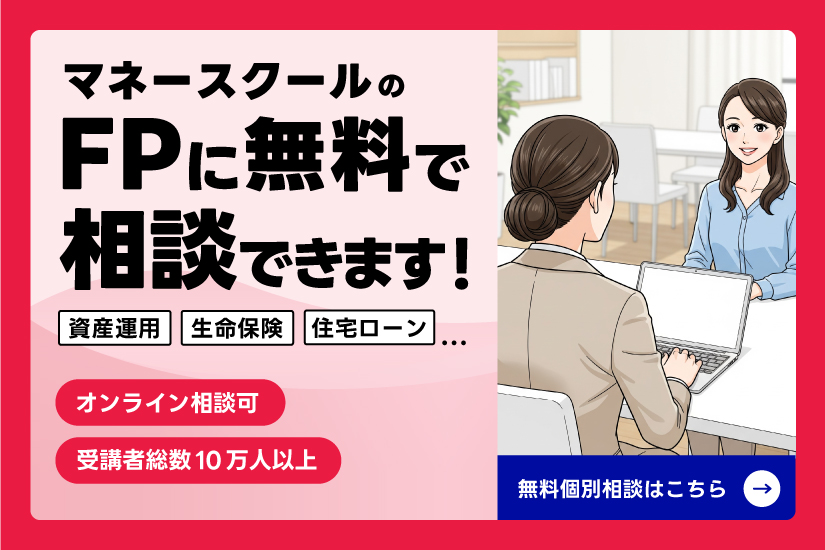「個人年金保険に入っているけど、年末調整で何かお得になるの?」
「個人年金保険料控除って言葉は聞くけど、結局いくら戻ってくるのかよくわからない…」
そんな疑問をお持ちではありませんか?
この記事では、個人年金保険料控除の基本から、いくら税金が戻ってくるのか、控除を受けられる条件、そして年末調整や確定申告での手続き方法まで、わかりやすく解説します。
この記事を読めば、あなたの疑問がスッキリ解決し、自信を持って控除の手続きができるはずです。

1:そもそも個人年金保険料控除とは
「個人年金保険料控除」とは、将来のために支払っている個人年金保険の保険料に応じて、その年の税金の負担を軽くしてもらえる制度です。
なぜ保険料を支払うと税金が安くなるのか、それは「所得控除」という仕組みにあります。
所得税や住民税は、1年間の「所得(儲け)」を基に計算されます。「所得控除」とは、この所得から一定の金額を差し引ける仕組みのこと。課税対象となる所得が小さくなるため、結果的に支払う税金が安くなるのです。
この個人年金保険料控除は、「生命保険料控除」という大きな枠組みの一つです。生命保険料控除には、他に「一般生命保険料控除(死亡保険など)」や「介護医療保険料控除(医療保険など)」があり、それぞれ別の枠として扱われます。
2:個人年金保険料控除額の上限と税金の軽減額
個人年金保険料控除を利用すると、具体的にいくら税金がお得になるのでしょうか。ここで重要になるのが「控除額」です。ただし、「控除額=手元に戻ってくるお金」ではないので注意が必要です。
ここでは、まず所得から差し引ける「控除額」の上限と、その計算方法について見ていきましょう。
2−1:個人年金保険料控除額の上限は所得税4万円・住民税2.8万円
個人年金保険料控除で所得から差し引ける金額には上限があります。現在主流の「新制度」の場合、上限額は以下の通りです。
- 所得税の控除上限額:最大40,000円
- 住民税の控除上限額:最大28,000円
これは、年間に支払った保険料が多ければ多いほど、たくさん控除されるわけではなく、それぞれの上限額までしか所得から差し引くことができない、ということを意味します。
例えば、年間の保険料が12万円(月々1万円)だとしても、所得税の計算上は4万円まで、住民税の計算上は2万8千円までが控除の対象です。
2−2:新制度と旧制度で控除額の計算方法が異なる
個人年金保険料控除の計算方法は、加入した保険の契約日に応じて「新制度」と「旧制度」の2種類に分かれます。どちらの制度が適用されるかで、控除額の計算式や上限額が変わるため、ご自身の契約を確認してみましょう。
- 新制度:2012年(平成24年)1月1日以降に契約した保険
- 旧制度:2011年(平成23年)12月31日以前に契約した保険
それぞれの所得税の控除額は、年間の支払保険料に応じて以下の表のように計算します。

出典:国税庁「旧生命保険料と新生命保険料の支払がある場合の生命保険料控除額」
もし新旧両方の制度の保険に加入している場合は、それぞれで計算した控除額を合算できますが、その場合でも合計の上限は4万円です。
3:個人年金保険料控除の適用条件を解説
個人年金保険料控除を受けるには、いくつかの条件をクリアしなければなりません。これを「個人年金保険料税制適格特約」と呼びます。この特約が付加されている保険だけが、控除の対象となるのです。
ここでは、ご自身の保険が控除の対象になるかどうかを確認するための、具体的な条件を見ていきましょう。
3−1:個人年金保険料控除を受けるための4つの条件
あなたの加入している個人年金保険が控除の対象となるためには、以下の4つの条件をすべて満たしている必要があります。
①年金受取人が、保険料を支払う本人(契約者)またはその配偶者であること。子どもや親が年金を受け取る契約は対象外です。
②年金受取人が、保険の対象となる人(被保険者)と同一人物であること。例えば、夫が契約者で妻が被保険者の場合、年金受取人も妻であることが必要です。
③保険料の払込期間が10年以上であること。5年など短い期間で保険料を払い終える契約は対象になりません。
④年金の受取開始が60歳以降で、かつ受取期間が10年以上(または終身)であること。年金の受取開始が55歳からだったり、受取期間が5年間の確定年金だったりする場合は対象外です。
これらの条件は、あくまで安定した老後資金の準備を促すという制度の目的に沿ったものになっています。
3−2:個人年金保険料控除が対象外となるケース
「個人年金保険」という名前がついていても、控除の対象にならない保険も存在します。特に注意したいのが、以下のようなケースです。
一時払いの個人年金保険
契約時に保険料をまとめて支払う「一時払い」は、「10年以上の払込期間」という条件を満たさないため、控除の対象外となります。
変額個人年金保険
株式や債券などで運用し、その実績によって将来の年金額が変動する「変額タイプ」は、年金額が確定していないため、原則として控除の対象にはなりません。
一部の外貨建て個人年金保険
海外の通貨で運用するタイプも、上記の条件を満たさなかったり、そもそも「税制適格特約」を付けられなかったりする商品が多くあります。
これらの保険料は、個人年金保険料控除の枠ではなく、「一般生命保険料控除」の枠で申告することになります。
3−3:条件を満たしているかは「生命保険料控除証明書」で確認
「4つの条件を全部チェックするのは大変…」と感じた方には、もっと簡単に確認する方法をご紹介します。
毎年10月〜11月ごろになると、保険会社から「生命保険料控除証明書」というハガキが届きます。証明書の中にある「個人年金保険料」という欄に、支払った保険料の金額が記載されているかを確認してください。もしここに金額の記載があれば、あなたの保険は個人年金保険料控除の対象です。
逆に、個人年金保険に加入しているつもりでも、証明書の「一般生命保険料」の欄に金額が書かれている場合は、その保険は個人年金保険料控除の対象外です。まずはこの証明書を確認してみましょう。
4:個人年金保険料控除の手続きは「年末調整」「確定申告」が必要
個人年金保険料控除の手続き方法は、あなたの働き方によって異なります。会社員や公務員の方は「年末調整」。一方、個人事業主やフリーランスの方は「確定申告」です。
どちらの手続きにも、保険会社から送られてくる「生命保険料控除証明書」が必須となりますので、事前に準備しておきましょう。
4−1:年末調整で控除を受ける【会社員・公務員】
会社員や公務員の方は、毎年秋から冬にかけて行われる「年末調整」で手続きを行います。勤務先から配布される書類に記入し、控除証明書を添付して提出するだけで完了するので、比較的簡単です。
手続きの基本的な流れは以下の通りです。
- 保険会社から届く「生命保険料控除証明書」を準備
- 勤務先から渡される「給与所得者の保険料控除申告書」を用意
- 申告書の中にある「生命保険料控除」の欄に、控除証明書に書かれている保険会社名、保険の種類、年間の支払保険料などを書き写す
- 新制度・旧制度の区分に従って控除額を計算し、記入
- 記入が終わった申告書と、控除証明書の原本を勤務先の担当部署に提出
記入する際は、「一般生命保険料」や「介護医療保険料」の欄と間違えないよう、「個人年金保険料」の欄に正しく記入してください。
4−2:確定申告で控除を受ける【個人事業主・フリーランス】
個人事業主やフリーランスの方は、年に一度の「確定申告」で所得税を納める際に、あわせて個人年金保険料控除の申告を行います。
手続きの流れは以下のようになります。
- 「生命保険料控除証明書」と、その年の事業の収支をまとめた書類を準備
- 確定申告書の「所得から差し引かれる金額」という項目の中に「生命保険料控除」という欄があるので、そこに控除額を記入
- 作成した確定申告書と必要書類を、定められた期間内に税務署へ提出
手書きで作成することもできますが、国税庁のWebサイト「確定申告書等作成コーナー」を利用するのがおすすめです。画面の案内に従って支払保険料などを入力するだけで、控除額を自動で計算してくれるため、ミスなく簡単に申告書を作成できます。
4−3:申告を忘れても5年以内なら還付申告できる
「年末調整の時に、うっかり申告書を出し忘れた…」「去年までこの制度を知らなかった…」という方も、諦めないでください。
実は、払い過ぎた税金を返してもらうための「還付申告」という手続きがあり、過去5年分までさかのぼって申告することが可能です。例えば、2023年分の控除を忘れた場合、2028年の年末まで手続きを行えます。
手続きは、お住まいの地域を管轄する税務署で行います。その年の「源泉徴収票」と「生命保険料控除証明書」が必要になるので、大切に保管しておきましょう。少し手間はかかりますが、払い過ぎた税金が戻ってくる可能性があるので、対象となる方はぜひチャレンジしてみてください。
5:まとめ
個人年金保険料控除は、将来の安心のために備えながら、毎年の税負担を軽くできる、有用な制度です。最初は「難しそう」と感じたかもしれませんが、ポイントさえ押さえれば、手続きは決して複雑ではありません。
まずは、保険会社から届いている「生命保険料控除証明書」を手元に用意し、ご自身の契約が控除の対象になっているかを確認することから始めてみましょう。
この記事を参考に、着実に手続きを進めて、受けられるメリットを最大限に活用してください。
6:マネースクール101の無料個別相談
「お金のことを相談してみたいけど、誰に相談してよいかわからない…」
「自分にあった貯蓄や節約の方法が知りたい」
そんな方は、まずは無料でFP(ファイナンシャルプランナー)に相談をしてみませんか?
ご相談は来店またはオンラインで全国どこからでも可能です。
こんなことが相談できます
- 家計の見直し、ライフプランの作成
- 住宅購入の予算、住宅ローンの選び方
- 老後資金、教育資金の貯め方
- NISA、iDeCoの始め方
- 保険の加入、見直し
など
お金に関することをわかりやすく説明しますので、初心者の方もお気軽にご相談ください。
無料相談をご希望の方はこちらから!無料個別相談はこちら