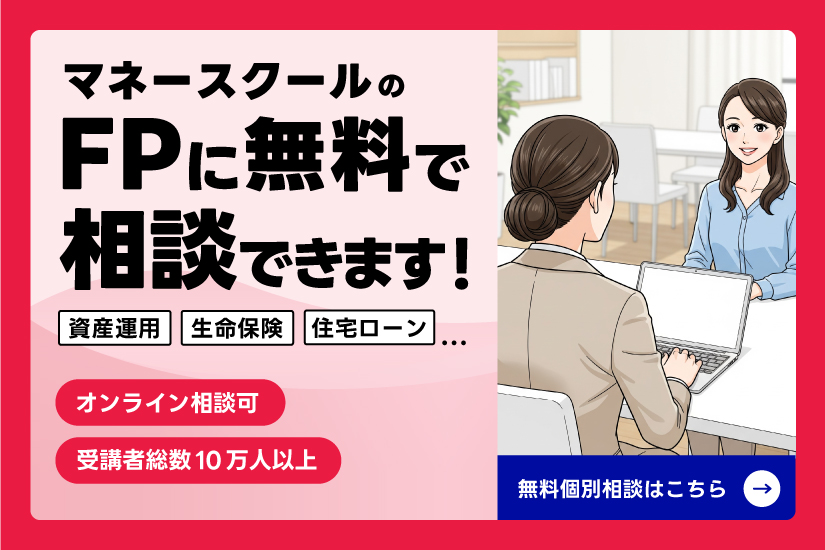「こんなとき、保険金の受取人はどうしたらいいんだろう?」
生命保険に入る際、このような悩みを持つ方は少なくありません。
というのも、昨今はパートナーや家族構成が多様化し、保険の受取人を誰にするかの選択肢が広くなっています。
この記事では、保険金受取人を誰にするか悩みやすい事例ごとに解説をしていきます。
また、家族構成や状況の変化によって、保険金受取人を変更した方が良いケースもご紹介。
あなたの悩みを解決できる内容になっておりますので是非読んでみてください。
この記事で分かること!
- 保険金受取人とは(指定範囲・税金の違い)
- パターン別保険金受取人の具体例
- 保険金受取人を変更するパターン例

1:保険金受取人とは
保険金受取人とは、生命保険や医療保険などで、契約者が亡くなったり保険事故が発生したときに、保険金を受け取る人のことを指します。
誰を受取人にするかによって、かかる税金の種類や税金額も変わるため、非常に重要になります。
例
- 契約者:夫
- 被保険者:夫(万一亡くなった場合に保険金が出る対象者)
- 保険金受取人:妻
この場合、夫が亡くなると妻が保険金を受け取ります。
しかし、受取人が妻ではなく子どもや両親になっていると、税金の扱いや手続きが変わることがあります。
では、保険の受取人は誰が、どの範囲まで対象となるのか?
また、税金の種類についても解説していきます。
1−1:保険金の受取人の指定範囲
生命保険の受取人は、基本的に契約者が自由に指定することができます。
基本的には、保険金受取人に指定できる範囲は配偶者と子どもや親など2親等以内の血縁者となっている保険会社が多いです。

1−2:保険金受取人の違いによる税金の違い
生命保険の保険金は、契約者・被保険者・受取人の組み合わせによって、かかる税金の種類が変わります。
保険金にかかる税金の種類は、主に3つです。


2:パターン別保険金受取人の具体例
昨今はパートナーや家族構成が多様化し、保険金の受取人をどうするか?に悩む方も増えてきました。
ここでは、以下の5つのパターンを例に、受取人候補と注意点を具体的にまとめました。
- シングル
- 内縁関係(事実婚)
- 同性パートナー
- 身寄りがいない
- 日本国籍以外
自分の状況に近いパターンを確認してみてください。
※受取人の指定できる範囲や条件は保険会社によって異なる場合があります。不明点は各保険会社に確認しましょう。
2−1:シングルの場合
独身で配偶者や子どもがいない場合に想定できる受取人候補です。
受取人候補
両親、兄弟姉妹、甥姪など。
注意点
・両親が高齢の場合、受取人が先に亡くなる可能性もあるため、第二受取人を指定しておくと安心。
・兄弟姉妹を受取人にした場合は相続税がかかる(非課税枠あり)。
・遠縁の場合、手続きや確認書類が増える可能性あり。
2−2:内縁関係(事実婚)の場合
婚姻届を出していないが、同居や生活を共にしている場合に想定できる受取人候補です。
受取人候補
内縁の配偶者(パートナー)
注意点
・保険会社によっては受取人指定が可能だが、住民票や同居証明などの書類提出が必要な場合がある。
・法律上の配偶者ではないため、相続税の非課税枠(500万円×法定相続人数)は利用できない。
・贈与税がかかることが多く、税率が高くなりやすい。
参照:ライフネット生命|事実婚のパートナーを死亡保険金の受取人にできますか?
2−3:同性パートナーの場合
同性パートナーを保険金受取人にしたい場合、以下の条件が必要です。
・都道府県自体あるいは都道府県内の全自治体で『同性パートナーシップ制度』がある
・パートナーシップ宣誓制度受理証明書がある
受取人候補
同性パートナー
注意点
・保険会社によっては受取人指定が可能だが、パートナーシップ証明書などの公的書類が必要。
・法律婚と同等の相続権はないため、相続税非課税枠は利用できない。
・贈与税の対象になる可能性が高く、保険金額によっては税額が大きくなる。
参照:ライフネット生命|死亡保険金受取人の指定範囲に、「同性のパートナー」を指定できます
2−4:身寄りがいない場合
親族がいない、または家族とは連絡を取りたくない場合に想定できる受取人候補です。
受取人候補
友人、信頼できる知人、福祉団体、信託会社など
注意点
・親族以外を受取人にする場合、保険会社の承認や理由書の提出が必要な場合がある。
・贈与税がかかるケースが多く、税率が高くなりやすい。
・信託を利用すると、死亡後に希望どおりの使い道(寄付など)ができる。
2−5:日本国籍以外の場合
受取人が外国籍または海外在住の場合に想定できる受取人候補です。
受取人候補
海外在住の配偶者、子ども、親族
注意点
・日本の相続税がかかる場合があり、非居住者でも課税対象となることがある。
・海外送金手続きに時間がかかり、追加書類が必要になる場合がある。
・外貨建て保険の場合、為替変動による受取額の増減リスクがある。
参照:三井住友海上あいおい生命|配偶者が外国籍で、帰化(日本国籍を取得)していません。配偶者を保険金受取人に指定することはできますか?
3:保険金受取人を変更するパターン例
保険契約では、結婚や離婚、家族構成の変化といったライフイベントによって、受取人を変更するケースもあります。
ここでは、変更が必要になりやすい代表的なケースと注意点を紹介します。
3−1:結婚した場合
結婚した場合、保険金受取人の変更を検討したほうが良い場合があります。
なぜなら、独身時代には親や兄弟姉妹を受取人にしていることがあるからです。
結婚後は、保険金受取人を確認し、受取人を配偶者や子どもへ変更することを検討してもよいでしょう。
注意点
・受取人を配偶者に変更する場合は、契約者本人の署名・押印で手続き可能。
・配偶者は相続税の非課税枠を使えるため、税制面のメリットが大きい。
・変更しないままだと、意図しない相手に保険金が支払われることがある。
参考:日本生命|結婚したとき
3−2:離婚した場合
離婚した場合、受取人が前配偶者のままだと、前配偶者にそのまま保険金が渡ってしまう可能性があります。
意図しない受取人に保険金が支払われることを防ぐため、速やかに受取人の変更手続きを行うことが重要です。
注意点
・受取人を子どもや親族に変更する場合、契約者本人の署名・押印で手続き可能。
・離婚後に親権を持つ側の子どもを受取人にするケースもあるが、未成年の場合は保険会社が支払い時に「未成年者の保険金受取」に制限をかけることが多いため注意が必要。
・離婚後の生活設計や相続対策を踏まえ、受取人を見直すことが大切。
参考:日本生命|離婚したとき
3−3:保険金受取人が死亡している場合
受取人が既に亡くなっているのに変更手続きを行っていないと、保険金は「契約者の法定相続人」に分配されることになります。
そのため、想定していた相手に保険金が届かない可能性があります。
注意点
・受取人が死亡した場合は、速やかに新しい受取人を指定し直す必要がある。
・受取人が複数いる場合は、亡くなった方の分は他の受取人に按分される。
・誰を指定するかによって、相続税や贈与税の課税関係が変わるので注意。
参考:生命保険文化センター|死亡保険金受取人が被保険者より先に死亡していた場合、保険金は誰が受け取る?
3−4:受取人が認知症になってしまった場合
保険金の受取人が認知症になった場合、受取手続きがスムーズに進まない可能性があります。
認知症の程度によっては、自分で請求手続きができず、成年後見人を立てる必要が生じるケースもあります。
注意点
・成年後見制度を利用すると、家庭裁判所を通じて後見人が選任され、後見人が保険金を受け取ることになる。
・成年後見制度には費用や時間がかかるため、事前に信頼できる家族を受取人にしておくなどの工夫も有効。
・生前の財産管理や相続対策とあわせて、保険金受取人の見直しを定期的に行うことが望ましい。
3−5:保険金を受け取る親族がいない場合
契約者が独身で子どももおらず、親や兄弟姉妹もいない(または既に他界している)場合、保険金を受け取る親族が存在しないことになります。
この場合、そのまま受取人を指定せずにいると、保険金は「相続財産」とみなされ、最終的には国庫に帰属する可能性があります。
注意点
・親族以外(例えば信頼できる友人や内縁のパートナーなど)を受取人に指定することも可能。
・親族以外を受取人に指定する場合、相続税の非課税枠は使えず、贈与税扱いになるため、課税が重くなる点に注意。
・「公益法人」や「任意団体」などを受取人に指定できる保険会社もあるため、社会貢献として寄付する形を選ぶこともできる。
・誰に渡すかを明確にしないままだと、意図せぬ形で国庫に帰属することになるので、早めの検討が重要。
参考:第一フロンティア生命|死亡保険金(給付金)受取人として指定したい人がいませんが、どうしたらよいですか?自分自身や相続人を指定できますか?
4:まとめ
保険金受取人は「契約時に一度決めたら終わり」ではなく、ライフイベントや家族関係の変化に応じて定期的に見直すことが重要です。
結婚・離婚・死亡・認知症・親族不在などのケースを想定し、意図しない相手に保険金が渡らないように管理していきましょう。
5:マネースクール101の無料個別相談
「保険金の受取人を誰にしたらいいか悩んでいる」
「加入中の保険の見直しをしたい」
そんな方は、まずは無料でFP(ファイナンシャルプランナー)に相談をしてみませんか?
ご相談は来店またはオンラインで全国どこからでも承ります。
こんなお悩みが相談できます
- 保険金の受取人を誰にすればよいか
- 必要な保障、保険の選び方
- 加入中の保険の見直し
- 保険料の節約方法
など
保険やお金に関することをわかりやすく説明しますので、初心者の方もお気軽にご相談ください。
無料相談をご希望の方はこちらから!